蛍の光 その2
こんにちは。音環境コンサルタントの齋藤す。
「蛍の光」についていろいろご感想ありがとうございます。
そもそもは、スコットランドの民謡で今の形になったのは1799年頃。
別れを惜しみ、すばらしい再開を願っての歌です。
1799年といえば、ベートーヴェンやモーツァルトが活躍した時代ですから、彼らも随分と親しんだそうです。
いろいろと伴奏を変えては演奏したとのこと。
なかなかの名曲なようですね。
日本では、まず卒業の曲として採用されました。
その後、主にパチンコ店での閉店音楽として使われ始め、それ以来多くのお店で閉店の音楽として使用されています。
有線のチャンネルに必ずあるというのも気軽に使う理由かもしれません。
その反応はと言えば、
調査の結果ではそれほど不快感は抱かれていないようです。
「ああ、閉店の時間か」
それくらいだという意見が多数でした。
コメントにも頂いた通り、昼間流れてしまったりしたら混乱するでしょうね。
いわゆる古典的条件付けであり、、「蛍の光」が流れたら特に意識することなく
「あっ、帰らなきゃ」と思うまで刷り込みされたのでしょう。
小さい店舗では特に流すことはなく大きな店舗での使用が多いようです。
お客さんとのコミュニケーションが取りやすいという点での違いでしょう。
不快感という観点では問題ないというのが結果です。
むしろ、閉店前に掃除を始めたり、あからさまに帰れと言っているお店の方が問題ありますね。
飲食店では外の電気を早々に消してしまうところもあります。食事くらいゆっくりさせてほしいものです。
私はよくヨドバシカメラに行くのですが、ここの店員さんは閉店5分前になっても外で呼び込みをしています。
こちらが驚いたほどです。
そんな時間にも関わらず、丁寧に商品の説明もして下さいました。非常に好印象だったのを覚えています。
そういった小さい気配りがお店の売上にもつながっているのだと思います。
ちなみに「蛍の光」が閉店音楽なのは日本だけだそうです。
ではまた。
この記事を書いている人
- Twitter:@fermondo
- 齋藤寛のFacebook(お気軽にどうぞ)
新潟大学教育学部芸術学科でピアノ演奏と音楽心理学を専攻。音や音楽が人の感情におよぼす影響について研究する。飲食店やオフィスなど商用BGMに関するコンサルティング、ビジネス書、専門誌への寄稿、医療学会での講演、ラジオ、テレビ、雑誌などメディア露出も多数。BGMアドバイザーとして音楽を提供する企業への協力や、個人向けに音楽心理カウンセリング(音で心を整える)をおこなうなどその活動は多岐に渡る。
著書に「心を動かす音の心理学」がある
最近の記事一覧
- 2015.06.10ピアノにまつわる話『ピアノ教室の法則術』が発売されました!購入者限定音声プレゼントもあります。
- 2015.04.13マスコミ取材関係新入社員の五月病を救え!BGMにできるメンタルヘルスケア
- 2014.12.13マスコミ取材関係オフィス街のお寿司屋さんのBGM ~スペースによって雰囲気を変える~
- 2014.08.25マスコミ取材関係会社の休憩室でのBGM選びのポイント

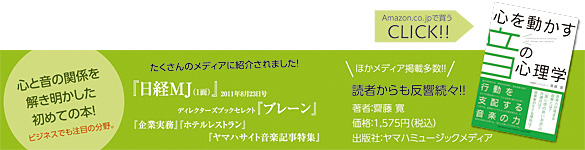
- 更新通知サービス 36 views
- 音環境コンサルタント-齋藤寛です。 37 views
- BGMでお店をブランド化 25 views
- 映像と音楽の関係 32 views
- ドライブに最適なBGM 29 views


 株式会社リーラムジカの藤拓弘先生の新刊『ピアノ教室の法則術~成功への7つの極意)』が発売されました。藤拓弘先生といえば、ピアノ教室のコンサルタントの第一人者として本当に大活躍されていますね。書籍も精力的に出版されてお......
株式会社リーラムジカの藤拓弘先生の新刊『ピアノ教室の法則術~成功への7つの極意)』が発売されました。藤拓弘先生といえば、ピアノ教室のコンサルタントの第一人者として本当に大活躍されていますね。書籍も精力的に出版されてお......  USENさんのプログラムガイド「WithMusic」で『BGMのギモン』と題して連載をしています。vol.05のテーマは「新入社員の五月病を救いたい」(笑)。BGMも五月病を救わなければならない事態になってきました。......
USENさんのプログラムガイド「WithMusic」で『BGMのギモン』と題して連載をしています。vol.05のテーマは「新入社員の五月病を救いたい」(笑)。BGMも五月病を救わなければならない事態になってきました。......  USENさんのプログラムガイド「WithMusic」で『BGMのギモン』と題して連載をしています。vol.04の今回はオフィス街のお寿司屋さんのBGMについて。地方都市のオシャレなお寿司屋さん。ランチの単価は2,0......
USENさんのプログラムガイド「WithMusic」で『BGMのギモン』と題して連載をしています。vol.04の今回はオフィス街のお寿司屋さんのBGMについて。地方都市のオシャレなお寿司屋さん。ランチの単価は2,0......  USENさんのプログラムガイド「WithMusic」で『BGMのギモン』と題して連載をしています。vol.03の今回は休憩室でのBGMの選び方です。会社の休憩室では気分を解放しすぎないのがポイント会社内の休憩室はリ......
USENさんのプログラムガイド「WithMusic」で『BGMのギモン』と題して連載をしています。vol.03の今回は休憩室でのBGMの選び方です。会社の休憩室では気分を解放しすぎないのがポイント会社内の休憩室はリ......  夏の暑い季節に必ず質問をいただくのが、「音楽で涼しさを演出できない」かというもの。連載をさせていただいているUSENさんの「WithMusic」でも夏に向けて涼感BGMの特集が組まれました。今回は音楽から涼しさを感......
夏の暑い季節に必ず質問をいただくのが、「音楽で涼しさを演出できない」かというもの。連載をさせていただいているUSENさんの「WithMusic」でも夏に向けて涼感BGMの特集が組まれました。今回は音楽から涼しさを感......  By:DavidGoehring普段音楽を聴くときは何気なくそのときに聴きたい曲を流していると思います。何となく、ビリー・ジョエル。何となく、ショパンのエチュード。何となくPUFFY。音楽って、その人の趣味趣向が濃......
By:DavidGoehring普段音楽を聴くときは何気なくそのときに聴きたい曲を流していると思います。何となく、ビリー・ジョエル。何となく、ショパンのエチュード。何となくPUFFY。音楽って、その人の趣味趣向が濃......  photo©2006IanWilson,Flickr音楽心理学を勉強したいという声を最近たくさんいただきます。こんなマニアックな学問に興味を示してくださりとても嬉しく思います。今回は、音楽心理学を勉強するな......
photo©2006IanWilson,Flickr音楽心理学を勉強したいという声を最近たくさんいただきます。こんなマニアックな学問に興味を示してくださりとても嬉しく思います。今回は、音楽心理学を勉強するな......  photo©2009PaulA.Hernandez,Flickr音や音楽はなぜ、私たちの感情をこうも左右するのでしょう。明るい音楽を聴けば、前向きな気持ちが湧いてくるし、悲しい音楽を聴けばちょっとセンチ......
photo©2009PaulA.Hernandez,Flickr音や音楽はなぜ、私たちの感情をこうも左右するのでしょう。明るい音楽を聴けば、前向きな気持ちが湧いてくるし、悲しい音楽を聴けばちょっとセンチ......  photo©2012HometownBeauty,Flickr好きな音楽を聴くだけで、運動能力がアップしなんと心臓病の症状も飛躍的に良くなったという実験結果が発表されました。それはセルビアのニス大学でのと......
photo©2012HometownBeauty,Flickr好きな音楽を聴くだけで、運動能力がアップしなんと心臓病の症状も飛躍的に良くなったという実験結果が発表されました。それはセルビアのニス大学でのと......  WomenClassicsウーマン・クラシック3タイトル同時発売キングレコードさんより大人の女性のための音楽「ウーマンクラシック」が発売されました8月7日に大人の女性のためのクラシックコンピレーションアルバム「......
WomenClassicsウーマン・クラシック3タイトル同時発売キングレコードさんより大人の女性のための音楽「ウーマンクラシック」が発売されました8月7日に大人の女性のためのクラシックコンピレーションアルバム「...... 






